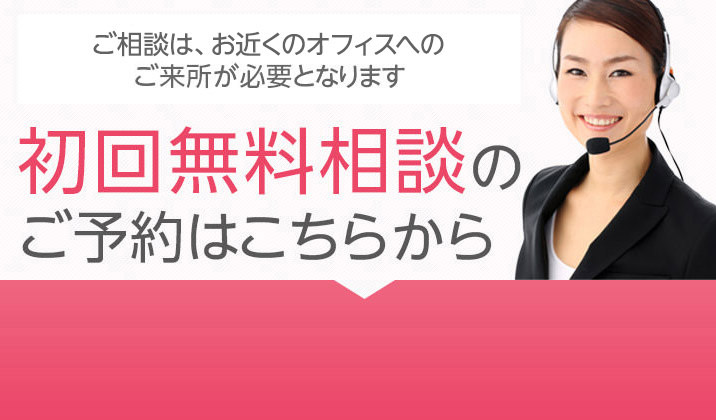離婚時に結婚前の貯金はどうなる? 財産分与や注意点を弁護士が解説
- 財産分与
- 離婚
- 結婚前の貯金

令和4年における三重県の離婚件数は2481組、離婚率は1.47(人口千人当たり)で、前年と同率でした。
離婚する場合、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる(民法768条1項)」と規定されており、財産を分け合う必要があります。しかし、「結婚前に貯金していた分も対象となるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。
今回は、結婚前の貯金は財産分与の対象となるのか、結婚前の貯金を証明する方法などについてベリーベスト法律事務所 四日市オフィスの弁護士が解説します。


1、離婚時に結婚前の貯金はどうなる?
離婚するとき、結婚前の貯金の取り扱いはどうなるのでしょうか。これも財産分与の対象となってしまうのでしょうか。
-
(1)結婚前から持っている貯金は財産分与の対象外
夫婦が結婚するよりも前から持っている現金・銀行預金などの貯金については、原則として「財産分与」の対象とはなりません。
財産分与とは、夫婦の実質的な共有財産を清算することを目的とする制度です。離婚後の生活に困窮する配偶者に対する扶養や、離婚によって精神的な損害を被った配偶者に対する慰謝料として機能しています。
財産分与の対象となる財産は、夫婦の婚姻期間中に取得された財産です。
したがって、配偶者と結婚する前から保有していた現金や銀行口座などの貯金については、婚姻期間中に獲得されたものではないため、財産分与の対象とはなりません。 -
(2)結婚前の貯金を使い込まれた場合
「結婚前の貯金を勝手に使い込まれていた」というケースがよく問題となります。生活費として費消されていた場合には、取り返すことが難しい可能性があります。
この場合には、夫婦の共同生活を維持するために使用されたと評価できるため、取り戻すことは難しいでしょう。
これに対して、相手の借金やギャンブルに浪費された場合には、返還請求ができる可能性があります。この場合には、相手が返還を拒絶するおそれがあるため、浪費した金額部分を証明できる必要があります。
2、財産分与の対象となるもの・ならないもの
それでは、夫婦が離婚するにあたっては、具体的にどのようなものを分け合う必要があるのでしょうか。ここでは、具体的に財産分与の対象となるものとならないものについて解説していきます。
-
(1)財産分与の対象となるもの
そもそも、財産分与の対象となるものは、夫婦が結婚している間に形成された共有財産です。
なお、結婚しているとしても、夫婦の協力関係が喪失したといえる場合(典型的には別居)には、その後に形成された財産は共有財産とはいえなくなります。
夫婦の共有財産に該当するものとしては、以下のようなものがあります。- 夫婦が居住用に購入した自宅不動産
- 結婚後に蓄えられた現金、銀行預金、有価証券
- 結婚後に購入された自動車
- 年金
- 退職金
結婚後に取得された不動産や預貯金、自動車や家具・家電などについては、一般的に財産分与の対象となります。特に、結婚生活に必要な家財道具などの動産については、共有持分が認められることが一般的です。
また、年金は「年金分割」という制度によって分け合うことになります。年金分割とは、夫婦の婚姻期間中に支払われた保険料の納付記録を分割して、それぞれ自分の年金として受け取れる制度のことです。年金分割の対象となるのは厚生年金のみで、国民年金(基礎年金)は分割の対象とはなりません。
さらに、退職金についても、給与の後払いという性質があるため、結婚期間に応じて将来受給が見込まれている退職金が分割の対象となることがあります。 -
(2)財産分与の対象とならないもの
財産分与の対象とならないものは、次のような財産です。
- 夫婦が結婚する前から保有していた不動産
- 結婚前に取得した預貯金、有価証券
- 結婚前から購入して使用している自動車
- 両親などから贈与、相続された財産
- 退職金のうち、独身期間に対応する部分
民法には、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で所有する財産)とする」と規定されています(民法第762条1項)。
このうち「婚姻前から有する財産」とは、結婚する以前に取得した不動産やブランド品、家具家電のほか、独身時代に取得した貯金も含まれます。
また、「婚姻中自己の名で得た財産」には、結婚期間中に相続や贈与で得た財産などを指します。なお、婚姻共同生活の中で各自が得た収入やその収入で得た財産については、実質的に夫婦の協力関係によって形成された財産と評価されることがほとんどですので、特有財産とは評価されず、原則的には共有財産とみなされます。
3、結婚前の貯金と証明する方法
結婚前の貯金であることはどのように証明すればいいのでしょうか。
一般的には、結婚前に取得された貯金については「特有財産」になり、結婚後に取得された貯金は「夫婦共有財産」と評価される可能性が高いでしょう。
貯金が特有財産であることは、結婚前の通帳の履歴や金融機関の取引履歴などにより証明することができます。たとえば、結婚する直前に通帳に記帳されている残高については、特有財産となる貯金であると証明することができます。
銀行などの金融機関の取引履歴については、窓口やオンラインなどで開示を請求することで取得することができます。しかし、一般的に銀行の取引履歴の保管期間は10年程度であることから、結婚期間が10年以上の場合には、すでに履歴が残っていない可能性もあるため、注意が必要です。
4、離婚前に知っておくべきこと
夫婦が離婚する場合には、財産関係以外にも取り決めておく必要がある事項が多数あります。ここでは、夫婦が離婚する前に知っておくべきことを解説していきます。
-
(1)子どもがいる場合は養育や親権を決める必要がある
未成年の子どもがいる場合、父母のどちらか一方を子どもの親権者に定める必要があります。親権者が指定されていない離婚届は受理してもらえません。
また、離婚後に子どもを十分に養育していけるように養育費の支払いについても取り決めておくことが重要です。
月々の養育費については、夫婦で話し合って自由に決めることもできますが、実務的には「東京・大阪養育費等研究会」が公表した算定表が用いられることが一般的です。
養育費が支払われる期間については、「子が成年に達する月まで」や、「子が大学を卒業する月まで」などと定めることになります。子どもが複数いる場合には、子どもごとに定めることになります。 -
(2)離婚後に住む場所を決めておく
離婚後に住む場所については、離婚前に決めておく必要があります。例えば、離婚後には賃貸マンションを借りたり、実家に住んだりするという方法があります。
地元から離れて仕事をしている方は、職場に近い場所の賃貸不動産を借りるという方法があります。子どもの親権者となった場合には、子どもの保育園の送り迎えや通学の都合を考えて住まいを決める必要があります。
ただし、賃貸マンションを借りる場合には、毎月の家賃を遅れずに支払う必要があり、収入や資産状況によって審査される可能性があります。
また、両親が健在で、離婚後の生活圏に実家があるという場合には、実家で生活するという方も少なくありません。マンションのように賃料が発生しないという以外にも、家事や育児のサポートが受けられるという点で、メリットが大きいでしょう。
離婚後に、生まれ育った実家で過ごすことで、離婚で負った精神的なダメージを癒やし、再出発のための療養期間となることにも期待できます。 -
(3)離婚に不安がある場合には弁護士に相談を
お一人で離婚手続きを進めていくことに不安を感じている方は、弁護士に相談するようにしましょう。
離婚事件を取り扱っている弁護士であれば、離婚相手との話し合いや交渉などを任せることができます。弁護士が代理人として対応するため、相手と直接やり取りをせずに済みます。
また、離婚調停や離婚訴訟などの裁判に発展した場合であっても、引き続き裁判手続きにも対応してもらえます。
さらに、相手方配偶者に不貞行為やDV行為があった場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。弁護士に相談することで、適切な慰謝料相場の請求が可能です。
5、まとめ
離婚する際、結婚前の貯金については、原則として財産分与の対象となりません。
ただし、相手が勝手に使い込んでいた場合や、返還を拒絶する場合などでは、結婚前の貯金の金額や費消された金額などを証明する必要があります。
結婚前の貯金の取り扱いについて不安がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。また、財産分与のほかに、養育費や慰謝料の取り決めなどに不安がある場合にも、弁護士に対応を依頼することで適正な金額を請求できます。
ベリーベスト法律事務所 四日市オフィスには、離婚問題の解決実績のある弁護士が在籍しております。まずはお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています