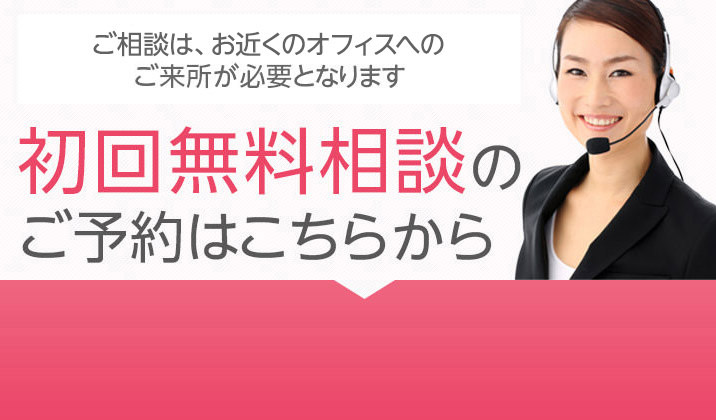結婚後の貯金は共有財産? 財産分与の対象となるものとは
- 財産分与
- 結婚後
- 貯金
- 共有財産

四日市市統計書によると、2021年の離婚件数は605件でした。離婚する際に気になることのひとつが、財産分与の対象はどこまでなのかという点でしょう。
夫婦で築いた財産は「共有財産」といい、分与の対象となります。また、この共有財産には結婚後に個人口座に蓄えた貯金も含まれます。
この記事では、どこまでが夫婦の共有財産となり、どのような財産が財産分与の対象となる・ならないのかについて、ベリーベスト法律事務所 四日市オフィスの弁護士がわかりやすく解説していきます。


1、そもそも共有財産とは?
-
(1)財産分与の対象となるのは共有財産
「共有財産」とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産のことをさします。夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、夫婦の協力によって形成されたものであれば財産分与の対象となります。
たとえば、結婚している期間に夫の収入で土地・建物を購入して夫の単独名義になっていたとしても、そのような財産は妻が家事を分担して夫を支えたことで得られた財産であるといえるため、夫婦共有財産となります。
また共有財産は財産分与の対象であり、民法では「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しています(民法第768条1項)。
このような財産分与請求権が認められている理由は、婚姻中に夫婦が共同生活を送る中で協力して蓄えた財産を離婚する際に実質的に公平になるように分けるためです。 -
(2)財産分与の割合は?
財産分与の割合は、夫婦の協議によって自由に決めることができるため、双方が合意できるのであればどのような割合でも分与可能です。
財産分与の割合に関連して民法には、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と規定しています(民法第768条3項)。
家庭裁判所の審判では、基本的に財産分与の割合は、「2分の1」とされることが多いでしょう。夫婦共働きのケースや、夫婦の一方が専業主婦(主夫)のケースのいずれであっても、共有財産を2分の1ずつ分けるように命じられるケースが多いといえます。
他方、一方の配偶者が共有財産の形成に特別の寄与をしたという場合には、分与割合の修正を求める当事者がそのような特殊な事情を適切に主張していく必要があるでしょう。
なお、財産分与には、離婚後の生活保障や離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると考えられており、離婚による慰謝料の金額を考慮して分与することも可能です。
2、結婚後の貯金は共有財産となるの?
-
(1)共有財産に該当するものとは?
婚姻中の夫婦の共有財産となるのは、以下のような財産です。
・現金、預貯金
結婚している期間に毎月働いて得た現金や預貯金については、原則として夫婦の共有財産と考えられます。
・土地や建物などの不動産
婚姻期間中に居住するために購入した不動産については夫婦の共有財産となります。婚姻中に夫婦の一方が他方に黙って購入した不動産についても、他方の貢献のおかげであるとして共有財産になる可能性が高いでしょう。
・株式、有価証券
婚姻期間中に購入した株式や国債、投資信託などの有価証券についても夫婦の共有財産となります。ただし、株式や投資信託などは評価価額の変動が激しいため、離婚時点での評価額を基準に2分の1ずつ分与することが一般的です。
・各種保険
婚姻期間中に契約した生命保険や学資保険などの各種保険についても、夫婦の共有財産となります。具体的な分与の方法としては、別居時又は離婚時のいずれか早い時点を基準に保険を解約して、その解約返戻金を2分の1ずつ分けるという方法をとることができます。
・家財道具、貴金属
婚姻期間中に購入した家財道具や家電、高価な貴金属についても夫婦の共有財産となります。貴金属や絵画、骨董品などについては、売却査定の評価額を基準に清算することができます。なお、ペットも法律上は所有権の対象のため、共有財産として清算の対象ですが、結婚前から買っていたペットであればその限りではありません。
・住宅ローンやカードローンなどの負債
夫婦の共有財産は、プラスの財産のみならず、住宅ローンやカードローンなどのマイナスの財産(負債)も対象となります。婚姻生活のための必要な負債については夫婦の共有財産となりますが、配偶者の一方のギャンブルなどによる借金は共有財産として考慮する必要はありません。 -
(2)財産分与の対象とならない特有財産とは?
財産分与の対象とならない資産を「特有財産」といいます。「特有財産」とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻中に自己の名で得た財産のことをさします(民法第762条1項)。
具体的に特有財産とされるのは、以下のようなものです。- 独身時代にためた現金、預貯金
- 独身時代にためた現金、預貯金で婚姻期間中に購入した財産
- 婚姻期間中に家族から相続した財産
- 別居後に取得した財産
以上のような財産については、夫婦の協力とは無関係に当事者の一方に帰属することになった財産ですので、離婚時に清算する必要はありません。
なお、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産については、夫婦の共有に属するものと推定されます(民法第762条2項)。
3、離婚時に共有財産を財産分与する際に覚えておきたいこと
-
(1)財産分与と慰謝料を区別するか決めておく
財産分与の合意をする場合には、「慰謝料と一緒に清算するのか、しないのか」を明確にしておくことが重要です。
この点を曖昧なまま手続きを進めてしまうと、離婚に際して慰謝料の支払い義務が発生しているケースでは、慰謝料を財産分与に含めた・含めていないという点で紛争が終結しないおそれがあります。
なお、判例によれば、財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とするものであるが、離婚による慰謝料を含めることもできるとされています。 -
(2)公正証書を作成する
財産分与や養育費の取り決めなど、離婚に際して当事者間で合意した事項については公正証書を作成しておくことがおすすめです。
公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書です。公正証書に「支払いを滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ない(「強制執行認諾文言」といいます)」といった内容を記載しておくことで、調停や審判といった家庭裁判所での手続きをせずに強制執行の手続きをとることができるようになります。
養育費や慰謝料、財産分与に関して金銭の支払いを公正証書で合意していたとしても、強制執行認諾文言の記載がなければ、公正証書によって強制執行することはできませんので、注意が必要です。 -
(3)財産分与を始める前に財産状況を明らかにしておく
財産分与を適切に行うためには、財産状況について明らかにしておく必要があります。
そのため、離婚や別居を検討し始めた段階で、相手方配偶者の財産状況を調査しておくようにしましょう。相手が財産を隠してしまった場合には、適切な内容で財産分与ができません。さらに、事後的に隠し財産が発覚した場合には、紛争が蒸し返されることになります。
前述のとおり、相手が財産を隠しているという場合でも、特有財産の場合には財産分与の対象とはなりません。分与の対象となる共有財産なのかどうかを判断できないという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
4、財産分与を決める流れ
-
(1)まずは夫婦で話し合う
財産分与については、まずは夫婦間でしっかりと協議することが大切です。
対象となる夫婦共有財産の範囲の整理・確認を当事者間で行うことが、スムーズに手続きを進めるためには重要です。
また、離婚に際しては、親権者の決定や養育費の支払い、子どもとの面会交流、婚姻費用の分担、慰謝料など、取り決めておくべき事項が複数あります。これらの離婚条件についても、夫婦間でしっかりと協議することが大切です。 -
(2)調停・審判などの裁判手続きを活用する
当事者間の協議では話し合いがまとまらないという場合には、家庭裁判所の調停や審判などの裁判手続きを利用することになります。
調停手続きでは、家庭裁判所の裁判官や調停委員2名が当事者から順番に話を聞き、双方が合意できる道を探ることになります。
このとき、弁護士のサポートを依頼しておくことで、証拠に基づいて適切に調停委員に主張してもらえたり、希望する条件で話し合いを進められたりする可能性もあります。また、煩雑な手続きの準備の負担もかなり軽減されることになります。
5、まとめ
結婚後に夫婦ふたりで貯金した金額については、基本的にすべて共有財産となります。共有財産か特有財産かの判断が難しいものに関しては、弁護士にご相談ください。
また、相手の財産の全体が把握できない場合も、弁護士に依頼することで、弁護士会照会などの財産調査を行うことができます。さらに、弁護士に相談することで、離婚慰謝料や養育費など財産分与以外の離婚条件についても、包括的なアドバイスやサポートを受けることができます。
離婚に関してお悩みを抱えている方は、一度ベリーベスト法律事務所 四日市オフィスの弁護士にご相談ください。解決実績がある弁護士がスムーズな財産分与のためにサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています