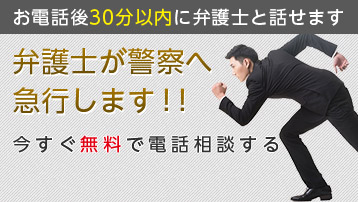他人を守るための行為は「正当防衛」になるか?
- 暴力事件
- 正当防衛
- 他人を守る

恋人や家族が暴力を振るわれそうになっている状況を目の当たりにして、とっさに加害者を突き飛ばしたり、殴ったりするなどの暴行をしてしまうこともあるかもしれません。
自分の身を守るために行動した場合には、「正当防衛」といえますが、自分以外の第三者を守るために罪を犯したときにも正当防衛は成立するのでしょうか。
今回は、他人を守る行為で正当防衛が成立するかについて、ベリーベスト法律事務所 四日市オフィスの弁護士が解説します。


1、「正当防衛」の定義や成立要件
そもそも正当防衛とはどのような制度なのでしょうか。以下では、正当防衛の定義と成立要件について説明します。
-
(1)正当防衛とは
正当防衛とは、一定の要件を満たす反撃行為について、犯罪としての違法性を免除する制度です(刑法36条1項)。
犯罪は、刑法などで定められた「構成要件」に当てはまる行為をしたことによって成立します。正当防衛が成立する場合には、この構成要件に当てはまるような何らかの違法行為をしてしまった場合でも、例外的に違法性が免除されることになります。
すなわち、正当防衛が認められれば犯罪行為をしたとしても、処罰されることはありません。
正当防衛が成立するためには、刑法が定める以下の5つの要件を満たす必要があります。 -
(2)正当防衛の成立要件|① 急迫不正の侵害
急迫の侵害とは、法益侵害の危険が現に存在している、または目前に差し迫っていることをいいます。
たとえば、「相手が拳を上げて殴りかかってこようとしている」、「相手から現在進行形で殴られている」という状況であれば、法益侵害の危険が差し迫っているまたは現に侵害されているといえますので、急迫性の要件を満たします。
他方、過去に殴られた仕返しとして反撃するような場合には、法益侵害の危険が差し迫っているとはいえませんので、急迫性の要件は認められません。 -
(3)正当防衛の成立要件|② 不正の侵害
不正の侵害とは、違法な侵害行為をいいます。正当防衛は、相手からの違法な侵害行為に対する反撃行為ですので、相手の行為が違法な行為といえない場合には、正当防衛は成立しません。
たとえば、相手が殴りかかってきたため、それを避けるために無関係の第三者を突き飛ばしたという場合には、第三者からの不正の侵害はありませんので、第三者を突き飛ばした行為については、正当防衛は成立しません。
この場合には、正当防衛ではなく「緊急避難」の問題となります。 -
(4)正当防衛の成立要件|③ 防衛の意思がある
正当防衛が成立するためには、行為者に防衛の意思があることが必要になります。
防衛の意思とは、急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態をいいます。そのため、この機会を利用して積極的に加害する意思をもち、相手に暴力を振るったなどの場合は、防衛の意思が否定されるため、注意が必要です。 -
(5)正当防衛の成立要件|④ 防衛の必要性がある
防衛行為の必要性とは、防衛のためにその行為をする必要性があったことをいいます。
逃げる余地があったにもかかわらず、積極的に攻撃をしかけたような場合には、防衛の必要性は否定されます。 -
(6)正当防衛の成立要件|⑤ 防衛行為に相当性がある
防衛行為の相当性とは、防衛行為が反撃の手段として必要最小限度の行為であったことをいいます。防衛行為の相当性は、「武器対等の原則」とも呼ばれ、相手の侵害行為に対して、行き過ぎた反撃をした場合には、正当防衛は成立しません。
たとえば、素手で殴りかかってきた相手に対して、ナイフで応戦するような場合には、防衛行為の相当性が否定される可能性が高いでしょう。
2、正当防衛は他人を守るための行為でも認められる
正当防衛は、刑法36条1項では、「自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」と規定されています。
すなわち、正当防衛は、自分を守るためだけでなく、他人を守るための行為でも成立します。そのため、家族や恋人が危険にさらされている場合に加害行為をしようとする相手を殴ってけがさせたとしても、傷害罪が成立することはありません。
3、「過剰防衛」や「傷害罪」に問われる場合
正当防衛には、2章で解説した通り「急迫不正の侵害」や「不正の侵害」など、複数の条件があります。
そのため、身を守るために相手を殴った際、これらの条件を満たさずに正当防衛が成立しないケースもあります。このような場合「過剰防衛」に問われる可能性があります。
-
(1)過剰防衛とは? 罪に問われるケース
過剰防衛とは、防衛行為として必要以上の力で対抗してしまい、適正な範囲を超えて反撃してしまうことを指します。
過剰防衛には、「量的過剰」と「質的過剰」の2つのパターンがあります。量的過剰とは、侵害行為が終わったにもかかわらず、必要限度を超えて反撃行為を継続した場合をいいます。質的過剰とは、素手による侵害行為に対してナイフで反撃した場合など防衛行為の相当性を逸脱した場合をいいます。
たとえば、「急迫不正の侵害」として相手が急に素手で殴りかかってきた際、自分や家族を守るために、ナイフを使って反撃をした場合、質的過剰となり得ます。
このような過剰防衛があった場合には、違法性は免れず犯罪が成立するおそれがあります。
ただし、過剰防衛は法律上の刑の減軽または免除事由とされていますので、裁判官の裁量によって刑が減軽または免除される可能性があります。 -
(2)過剰防衛として傷害罪に問われるケース
過剰防衛の「量的過剰」から、傷害罪に問われるケースもあります。
たとえば、夜道で突然襲われ、とっさに相手を殴り倒したが、相手が倒れたあとも何度も蹴る・殴るなどして重傷を負わせた場合、量的過剰として傷害罪になるおそれがあります。
傷害罪とは、他人の身体を傷つけた際に科される罪で、罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。過剰防衛と認定された場合、傷害罪の罰則よりは軽減されますが、相手の症状の度合いによっては懲役刑が科される可能性もあるでしょう。
4、他人に暴力を振るったなら、すぐに弁護士に相談を
他人に暴力を振るってしまったときは、刑事事件になる可能性がありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)正当防衛が成立する状況であるか判断できる
正当防衛の成立要件を満たすかどうかは、法的判断が必要になります。
自分では正当防衛だと思っていても、実際には正当防衛が成立せず罪に問われる、過剰防衛となる、といったケースもあります。正当防衛が成立するかどうかによって、今後の対応が大きく変わってきますので、まずは弁護士に相談して、正当防衛が成立するかどうかを判断してもらうとよいでしょう。 -
(2)逮捕された場合にサポートしてもらえる
暴力事件となった場合、警察により逮捕される可能性も否定できません。警察により逮捕されると警察署内の留置施設で身柄を拘束され、取り調べを受けることになります。
初めての取り調べで不安な状況だと、早く楽になりたいという思いから、やってもいないことをやったと供述してしまうケースも少なくありません。供述内容は、供述調書にまとめられ裁判の証拠となり、あとから覆すのは非常に困難となります。
そのため、警察による取り調べを受ける際には、刑事事件の実績がある弁護士によるアドバイスやサポートが不可欠になります。逮捕中に面会してアドバイスできるのは、弁護士だけです。早めに弁護士と面会することをおすすめします。 -
(3)被害者との示談により有利な処分を獲得できる可能性が高まる
被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談を成立させることにより、早期の身柄解放や不起訴処分といった有利な処分を獲得できる可能性が高くなります。
正当防衛が成立するようなケースであれば、被害者との示談は不要ですが、正当防衛の成否が争われるケースでは、起訴されて有罪になるリスクを考えると、早期に被害者と示談を行い、不起訴処分の獲得を目指した方がよいケースもあります。
正当防衛の事案で示談をすべきかどうかは慎重な判断が必要になりますので、まずは弁護士に相談して今後の対応をアドバイスしてもらうとよいでしょう。示談をすべきという結論に至ったときは、弁護士が本人に代わって示談交渉を行います。
5、まとめ
正当防衛は、自分だけでなく他人を守る場合でも成立します。ただし、積極的な加害意思があったり、過剰な防衛行為であったりすると正当防衛の要件を満たさず、犯罪が成立することになりますので注意が必要です。
相手からの違法な侵害行為に対する反撃行為が罪に問われそうな場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。まずはベリーベスト法律事務所 四日市オフィスまでお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|